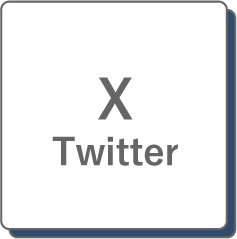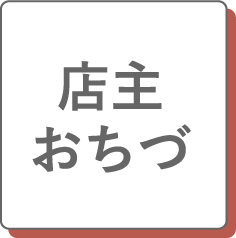備前焼茶器 -chitreeオリジナル-
商品について
店主おちづの一言
薬草茶を作り出した12年前から、こんな茶器があったらいいのにってずーーーと思っていたけど、自分で陶器を作るとか・・・
果てしない〜って思いながら生きていた。
そして、(夫)ひろしという旅人に出逢い、ひろしが旅中にお世話になった窯元へ、こんなもん作って欲しいと依頼したのが始まり。
焼き物は、蓋と容器を合わせるのはすごく大変って知ってた?
乾燥や焼きで縮み幅は焼き終わらないとわからない。
一回目は蓋とカップが合うものが少しだけしかできず、ほとんど商品化できなかった。
だからといって、またすぐ次のを作る!ってのは、無理な話。
また一から土作りをして、練って、窯焼き用の薪を準備して・・・
焼きにはいるまでに想像以上に手間暇がかかる。
だから、今回の窯焼きもドキドキ。
そして、前回のことも含めて窯元さんの経験と知識で今回たくさん仕上がりました!!!
嬉しすぎる〜。
機械生産でない、一つ一つ手作業。
土は生きていて呼吸していて、空気や火の加減で似ているようですべて一点もの。
備前焼に拘った理由は、備前の土は水を浄化する力がある。
昔は汲んできた水を、備前の壺に入れて最低1日は寝かしていたらしい。
お酒も一日中入れて待つんだとか。
釉薬でデザインされたものも好きだけど
私はやっぱり飾らない備前焼が一番好き。
しかも手間暇かけてみなきゃわからない登り窯で作ってる昔ながらの伝統文化が好き。
こうゆう伝統にふれると、伝統を日常使いできていた時代に生活したいと思う。
そんでもって、いったいどんな茶器かというと。
ポットに茶葉入れて、湯呑みに出すという手間がちょーめんどくさい。
それが好きって人もいるし、2人以上でわけわけするにはポットはいいけど、一人の時に1人分欲しい。
洗い物が増えるのが嫌で飲むのやめたり・・
わざわざ淹れるの手間やん。
やーめた!!
湯だけでいいや。って
湯だけもなぁー。
なんて。
だから、1人分。
抽出もして、そのまま飲みたい。
蓋の役割も重要。
湯気にも養分入ってるし、保温にもなる。
そんで煮出したら、蓋をひっくり返して茶漉しをポンと乗せるだけ。
茶漉しもマックスでかいのでわたしのこだわりの薬草でかめがしっかり湯の中で踊ってくれてしっかり抽出される。
私が作ったらやっぱり
ええものしかできんーーー。
それを叶えてくれた窯元さんに感謝。
・最大容量:370ml
・ハーブ茶を飲む場合の目安
3gの茶葉に300ml
1つ1つ手作りなので、多少の誤差はご了承ください。
備前焼きとは
備前焼は、良質の陶土で一点づつ成形し、乾燥させたのち、絵付けもせず釉薬も使わずそのまま焼いたもので、土味がよく表れている焼き物です。
焼き味の景色は、胡麻・棧切り・緋襷・牡丹餅などの変化に富んでいますが、それらは作品の詰め方や燃料である松割木の焚き方などの工夫と、千数百度の炎の力によって七〜十昼夜かけてじっくり焼き締めた硬質の炻器(せっき)が備前焼です。
一点として同じ形も焼き味も同じものは無いと言えます。
備前焼の土
備前焼の原土は伊部周辺の地下にある粘土層で「ひよせ」といいます。採土できる所は極わずかで貴重です。
作品の種類、作家の好みで山土を混ぜて使うこともあります。
ひよせは、粘りが強く耐火度は低く、陶土としては鉄分が多いです。釉薬を使わないだけに、備前焼では土に神経を使います。土づくりは、作家にとって重要な仕事です。
ご購入時の注意
備前焼は一つ一つ手作りで作られているため、色合いや形などが一つ一つ異なります。
そのため写真のものと同じ色・柄のものをお送りするわけではございませんので、予めご了承ください。
店主おちづにLINEで相談できます。お気軽に公式LINEでお問い合わせください
〈 公式LINE 〉
※LINEは24時間受付しておりますが、返信に多少のお時間いただく事があります。
@chitree organic All Rights Reserved.